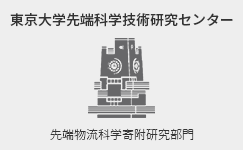第11回国際フィジカルインターネット会議(IPIC2025)参加報告
2025年6月18日から20日にかけて、香港・香港理工大学にて開催された「第11回国際フィジカルインターネット会議(11th International Physical Internet Conference, IPIC2025)」に、本研究室から井村プロジェクトリサーチフェローおよび江崎プロジェクトレクチャラーが参加しました。
本会議では、ヨーロッパ、アメリカ、日本などにおけるフィジカルインターネット(PI)の実現に向けたロードマップやその現状についての発表に加え、各国の大学における先進的な研究成果の共有が行われました。
会議には、香港、中国、欧州、日本、アメリカ、韓国の大学や政府機関から約150名の研究者・関係者が参加しました。日本からは、JPICの森先生、ヤマト運輸の梅津様、hacobuの坂田様によるパネルディスカッションが行われ、ヤマト運輸が最近発足させた「SST(Sustainable Shared Transport)」や、hacobuによる「物流ビッグデータラボ」といった、共同配送に関する取り組みが紹介され、活発な議論がなされました。
学術的な観点では、PIの提唱者であるジョージア工科大学のMontreuil教授が、ハブで構成される物流ネットワークを、ラストマイル、ローカルエリア、ゲートウェイといった地域スケールに応じて多層化し、2次元ではなく3次元として構想している点が印象的でした。
会議の発表・議論の多くは、欧州におけるPIの実装フェーズ加速に向けた取り組みに集中しており、AIとの連携、国際標準やガバナンスの整備といったテーマも多く取り上げられました。特に、欧州の物流革新団体「alice」が、EUの支援と200社以上の企業ネットワークを活かし、多数のPI実証プロジェクトを推進している点は注目されます。
日本においては、政府主導でロードマップが策定されたことは大きな成果である一方、その実現には欧州同様、産学官が連携した多くのパイロットプロジェクトの推進が不可欠です。今後、JPICの活動のさらなる充実が期待されます。